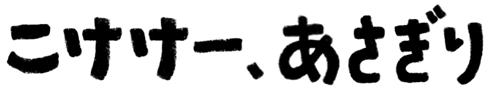2025.9.16
【田んぼに罪はない!】素人会社員が挑む有機米作り。想定外の「トリプルパンチ」

今年の春、主人は初めての「お米作り」に挑戦しました。
選んだ栽培方法は、有機栽培でのお米作り。
一昨年までは、京都で会社員として働くごく普通の暮らし。田んぼとは無縁の毎日でしたが、娘のアレルギーをきっかけに 、食の安全や環境への関心が芽生えました。
「この子が毎日食べるものは、本当に安心できるものだろうか?」
そんな小さな問いが、やがて大きな転機になりました。

京都でもアレルギーの娘と共に農家さんを訪問し学ぶ日々
その後移住を決め、あさぎり町で実施されている有機農業勉強会に通い始めました。
そこで見たのは農薬も除草剤も使われていないのに、驚くほど美しい田んぼ
。
「自分たちでも、こんなふうにお米を作ってみたい」と思ったのが、去年の秋のことです。
そしてこの春、ご縁が重なり、念願の田んぼをお借りすることに。
こうして、主人の“はじめてのお米作り”が始まりました。

球磨郡でお世話になっている有機農業勉強会の皆さま
雑草のない田んぼを目指して
スタートの段階から意識していたのは、土づくり・水の管理・ジャンボタニシの活用。これらが雑草の生えない田んぼのポイントだと勉強会で教わっていたからです。

雑草が生えない、美しい田んぼ!
勉強会では、“土づくりは秋から始まる ”と教わりましたが、田んぼを借りられたのが春。
それでもやらないよりはやった方がいいと、ベテラン農家さんから肥料の作り方を教えていただき、機械を持っていない主人は花咲じいさんのように手で肥料を撒き(笑)、ど素人感満載で田植えをスタートさせました。

手で撒く肥料の一部(笑)
全て手植えで行えればと、イベントを開催し地域の方にも手伝っていただきました。
イベントの様子はコチラをご覧ください!
しかし、その後の作業を主人ひとり、しかも仕事をしながらは確実に無理だ、ということに気づき(気づくのが遅い笑)、途中から農家さんが機械を出してくださり、足りない稲まで提供してくださり、皆さまに支えられてやっと田植えが終わりました。

仕事終わり、陽が沈むまで田植えをし限界を感じる(笑)
最初のうちは順調で「いい感じ!」と心の中でガッツポーズをしていたのですが、ある日気づいた衝撃の事実。。。
水が来ない、タニシがいない、草が伸びる…
ある日、田んぼの水位が下がっている ことに気づきました。
「あれ? 水路に何か詰まってる?」と水路の草掃除。

水路に詰まる草たち・・・
それでも水は来ず、周りの農家さんに聞いてみると「このあたりは川の下流だから、繁忙期は水が回ってこないんだよ 」とのこと。しかも、1週間以上水が来ないこともある。
“水の調整をしながら雑草の管理をする ”と学んでいましたが「水、来んのかーい」とひとりつっこみ。

カラカラの土壌・・・
そのうちに仕事が忙しくなり、数日間田んぼに行けなかった時期がありました。そして久しぶりに訪れた田んぼを見て、言葉を失いました。
草、爆発。
稲と仲良く育っている雑草たち。。。

ヒエさん、アワさん、こんにちは(泣)
もともとこの田んぼは牧草地だったため、期待していたジャンボタニシがおらず。草を食べてくれる救世主は不在 でした。
「ジャンボタニシ、おらんのかーい」とまたまたひとりつっこみ。
秋からの土づくりもできなかった我が家の田んぼは、土・水・タニシという三本柱のすべてが不在の「トリプルパンチ状態 」に陥ってしまいました。
雑草だらけの田んぼと、心の葛藤
毎月の勉強会で農家さんたちに状況を見てもらうのですが、私たちの田んぼを見て皆さん沈黙。。。あまりの草の量に、誰もが苦笑い。
「え!?これって素人が仕事しながらやるの無理じゃない?!」
と心の中で叫び、泣きそうになるのをこらえ、すごくすごく悔しい思いをしました。
そしてつい「田んぼが嫌いになりそう 」と口から出てしまいました。

雑草の生えない田んぼとは程遠い・・
救われた言葉と、もう一度向き合う決意
そんな時、有機農業勉強会メンバーの農家さんが、ぽつりと声をかけてくださいました。
「田んぼに罪はないからね 」
・・・その通りだ。
そして続けて
「予想していたよりは、いい感じだよ」
「稲は元気に育ってる。地力はある」
と勇気づけてくださいました。

いつも助けてくださる勉強会メンバーの皆さま
雑草で心が曇っていたけれど、田んぼ自体は変わらずそこにいて、稲はしっかりと生きている 。ここで田んぼまで嫌いになってしまったら、稲さんに申し訳ない。
皆さまの温かな言葉に助けられ、気持ちを切り替えることができました。
刈り取りのときは苦労するかもしれないけど、今のベストを尽くして、収穫まで走り抜けよう、そう心に決めました。
この経験が、誰かの希望に・・・
今回こうして記事にしているのは、ただの愚痴や失敗談ではありません。
農家さんが減り、田んぼが減り、お米が少なくなっている現代、これからは農家さんだけでなく、私たちのように「自分たちでお米を作ってみたい」という人が、きっと出てくるはず。

友人のお手伝い。このときは我が家でお米を作るなんて思ってもいなかった・・・
そんなとき、不利地域でお米作りを実施している主人の「トリプルパンチ」でもやってみた経験 が、どこかの誰かの役に立つのではないか。そう思って筆を取りました。
そして、不利地域と嘆くことも贅沢に感じるほど、私たちには手厚い地元有機農家さんたちの支えがあります。そんな環境にいる私たちが、ここで諦めるわけにはいかない。この経験をきちんと残していくことが、私たちのできることだと改めて感じました。

穂が付き始めた、愛する田んぼちゃん
ある農家さんから「湯前町の那須さん(84歳)は、勉強会以外でも君たちの田んぼを見に来て様子を伺っておられるんだよ」と教えてくださいました。車で30分はかかる距離、往復1時間かけて足を運んでくださっている事実。
この手法を少しでも紡いでいきたい
那須さんの強い信念を感じ、今回のお米作りが私たちの失敗か成功かなどでは到底測れない、未来への一歩なのだと感じることができました。

30年以上のキャリアを持つ那須公一郎さん
来年からはもう無理だと正直思うときもあるけれど、ここから逆転した姿を那須さんに見てほしい、今はそんな気持ちの方が強いです。

尊敬する那須さんを囲んで
さて今年の収穫はどうなるか・・・
素人会社員の挑戦はまだまだ続きます、、、!