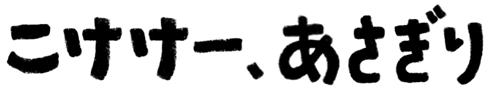今回は、あさぎり町上地区にあるお茶屋さん「松本製茶」様へのインタビューです!
あさぎり町出身の松本さん。
実家のお茶屋さんを継がれ、夫婦で協力してお茶の生産・製造から販売まで行われています。
約35年間続けられている、農薬不使用のお茶に込められた思い、背景とは…。
松本製茶さんの歴史
元々学校教師だった松本さんの父。松本さんの本家は林業とお茶屋さんを営んでおり、そのお茶屋さんを継いだのが昭和の初期のこと。もう100年近くなるそう。
大学卒業後は、従兄弟が横浜で営んでいたお茶屋さんで働いていた松本さん。その後は地元に帰ってくるようにとの声もあり、家業の手伝いをするようになったとのことです。

Yufuka
地元に帰ってきた時から、家業を継ごうと思っていらっしゃったんですか?

松本さん
一人息子なので、マインドコントロールで(笑)

Yufuka
そうなんですね(笑)

松本さん
それが当たり前の世界だったから。他の考えとか入る余地なかったね。

Yufuka
そうなんですね。続けていて「もう嫌だ!」と思うことはなかったんですか?

松本さん
いやー、それはなかったね。

お茶屋さんを継いだ当時の様子
当時はお茶の生産に加え、加工も忙しかったそう。
工場にある機械が大きく、他の事業者さんが作ったお茶や、近くの高校で収穫したお茶も松本さんの工場で加工をされていました。
近くにあるお茶の研究所のお茶加工も行い、とにかく加工に忙しい毎日だったそうです。
無農薬のお茶作りを始めたきっかけ
長男さんがアトピーを発症し「農薬を使うと子どもをすぐに抱っこできない」ことをきっかけに、農薬不使用でお茶を育てることに。息子さんへの思いと共に始まった無農薬栽培を35年間続けられています。

松本さん
息子がアトピーだったので、それをきっかけに農薬を使わないお茶の栽培を初めて、そこから約35年続けてる感じですね。

松本さん
まあ、その頃からお茶の売上が少しずつ落ちてきて、なにかしないと、とは思っていたので、そのタイミングで無農薬をはじめました。おかげで今は少しですが顧客も付いてきました。

お茶農家の一日
【午前】お茶畑で収穫
・収穫量は、なんと約1トンも!
【午後】収穫した茶葉を工場の機械で加工する
・お茶の葉をコンベアで流し、蒸気で蒸す。
・熱風の出る機械を使って茶葉表面の水分を飛ばす。
・焙煎、茶葉の大きさごとの選別、重さごとの選別、色ごとの選別をしてお茶が完成!

Yufuka
そんなに選別するんですね!だからラインナップがいっぱいあるんですか?

松本さん
そうです。
それもありますし、収穫の最初の方の新芽は小さいから、新芽の方がいいお茶ができるんです。
そういうお茶は高級なお茶として出します。
松本製茶さんでは、緑茶に加えてほうじ茶や紅茶も作られています。
使っている素材は同じですが、製法に違いがあるようです。

松本さん
ほうじ茶は焙煎用の機械で、緑茶の葉を焙煎して作ります。

松本さん
紅茶は、乾燥させたあと生葉のまま圧をかけて揉みこみます。葉っぱの表面に傷を付けるイメージです。
そうすることで発酵が始まって、発酵させた葉を紅茶にしていきます。
時代によって変わるお茶の作り方
以前は浅く蒸すことが多かったお茶。現在は深く蒸す方が需要があると松本さんは話されます。
きっかけは静岡方面で深く蒸すお茶が出始め、関心を持つ人が増えたこと。
深蒸しと浅蒸しでは、火を入れる加減(焙煎)が変わるのだそうです。

松本さん
普通、新茶の香りを出すためには30秒ほど蒸すのに対し、深蒸しの場合は1分半~2分ほど蒸し器の中に入れて蒸します。

松本さん
深く蒸すと急須で入れた時に綺麗な緑色のお茶が出るようになるんです。
逆に浅く蒸すと黄金色のようなお茶になります。

松本さん
田舎のお茶は火の香りがしません?番茶とかも。浅蒸しは香ばしい香りが特色です。深蒸しは火の香りはしないですね。
静岡の方では、深蒸しと浅蒸しのお茶の葉を混ぜ、緑色を出しながら香ばしさを出すようなブレンド茶を出されているそう。
松本製茶さんのお茶はブレンドしていないお茶を意味する、シングルオリジンと書かれています。
お茶の葉の収穫と管理
お茶の収穫シーズンや手入れについても聞いてきました!

松本さん
4月に1番茶を摘んで、6月初旬に2番茶を摘みます。
昔はお盆明けも摘んでいました。
収穫時期以外はお茶園の管理をしています。
【お茶園の管理】
草むしり
お茶園を綺麗に保つ
「耕種的防除」:虫や病気予防にお茶の木をカットする
(虫が付かないよう、最初から上側の葉っぱを全部切っておく)など
生葉の窒素量を測る機械があり、窒素の量でお茶の値段が変わるそう!
だからこそ、お茶園の管理をとても丁寧に行われているそうです!
お茶の管理に湿気は大敵。
あさぎり町は湿気も多く、お茶を保管する袋をすぐに閉める、天気がよい時を選んで作業をするなど、管理には気をつかわれているそうです。
特に粉末緑茶は湿気が入らない場所で作る必要があります。
工場内には区切られた専用の部屋があり、部屋の中はお茶の香りに満たされていました。


松本さん
この部屋は乾燥機やエアコンで除湿をしてます。湿気が多いとお茶の葉が湿気を吸って扱えないので、この部屋を作りました。
部屋の中には電動のセラミックの石臼があって、そこで粉末緑茶を作ってます。

自然の力と循環
虫が付いたお茶の葉を刈り取るとクレームに繋がると聞いたことがありますが、実際そのような声はあったのでしょうか。

松本さん
ずっと無農薬でお茶の栽培をしていたら虫が付かなくなりますよ。虫が付いたお茶の葉も少しはあるけど、そんな量はありません。
虫が付く前や病気になる前に収穫して、早め早めにやればそんなに問題ないよ。

松本さん
農薬を使ってなければ害虫も出てくるけど、それを食べられる虫も出てくる。例えばカマキリとか!
薬を使えば益虫まで殺してしまうからね。
最後に
最後にどのような思いでお茶を作られているか教えてください!

松本さん
「健康、安心と安全ですね。美味しいお茶をみなさんに飲んでほしいと思っています。」

ありがとうございました!